
注意
このページを読んだら、必ず自分の体で試してください。試さないで、言葉にしてはいけません。
「感じて理解する解剖」があります。
「頭を使って動きましょう」といっても、「考える」のとは違います。体の一部として「頭」を使うのです。
今までの解剖の説明でおわかりのように、首と頭のつなぎ目はどの方向にでも動くようにできています。
後頭顆と環椎の関節では、「うなづく動き」と「小首をかしげる動き」をまかなっています。
環椎と軸椎の関節では、「頭を回す動き」をまかなっています。
頸椎全体で、「首を前後に曲げる動き」、「首を横に倒す動き」、「首をひねる動き」をまかなっています。
これらの動きが組み合わさって、「頭から首の動き」を作っています。
そして、この「頭から首の動き」が「背骨全体の動き」に影響しています。
実験 1
立ち上がるときに、「うなづく動き」から開始して、「首を前に倒す動き」につなげて、胸を前に屈め、腰を緩く曲げて見てください。
「頭が先導して、首、胸、ウエストを引っ張っていく。その引きの力で骨盤が前に傾いて、お尻があがる」と思ってください。
そのように感じて、動いたときの「動きの質」はどんなものでしょうか?つらいでしょうか、気持ちよいと感じるでしょうか?
実験 2
老人に見られるような立ち上がり方をしてみます。
立ち上がるときに、頭の後ろの筋肉を緊張させて、頭をのけぞらせてください。
上半身をそのままにして前に倒し両足に重さがかかったら、お尻を椅子から浮かせて立ち上がります。
そのように感じて、動いたときの「動きの質」はどんなものでしょうか?つらいでしょうか、気持ちよいと感じるでしょうか?
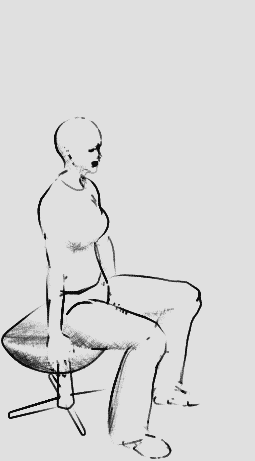
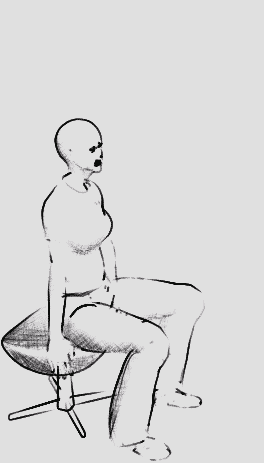
探求するもの
それぞれの立ち上がり方で、「頭」は背骨に対してどのような力をかけているでしょうか?引っ張っていますか、押していますか?
このような2種類の立ち上がりで、足首の関節、膝の関節、股関節はそれぞれどのように動いていると感じるでしょうか?
前に?後ろに?右に?左に?上に?下に?
足の裏のどこで重さを支えていると感じますか?その「重さを支えているところ」は、立ち上がる途中で変化しませんか?
どちらのほうがバランスを取りやすいでしょうか?
体全体のバランスはどこで調節しているのでしょう?
自分の背骨は「どこからどこまで」あると感じるでしょうか?
座って「うなづく動き」を開始したときに、お尻にかかっている重さは変わりますか?そのとき、骨盤は動いていますか?
うなづいて立ち上がるときと、のけぞって立ち上がるときに股関節の曲がる深さは同じですか?
両方の立ち上がり方を比べてみて、「骨盤を浮かせる力」はどこから来ていると感じますか?
ここにあげた「探求項目」は、力学的に「考えて」正解を求めてはいけません。
ここにあげた項目は「感じる」ために掲げました。これらのことを「感じていない人」は、他の人が立ち上がるときに、どこにどんなお手伝いをすればよいかわかりません。
ここにあげた「探求項目」には、みんなに共通する解答はありません。あなたとわたしの感じるものを、「同じ言葉」で表現できる保証はありません。
自分だけにわかる言葉で、自分の動きを自分に対して説明してください。
そうすれば、動きについて「外言」を作ることになります。「外言」を作れたら、はじめて、それを使って思考することができます。これが内言です。
上の探求を終えたら、自分で質問を作ってください。問題を見つけることができることが、創造性の証明です。
ここにアニメーションとして見せた立ち上がり方が、「正しい」のではありません。また、「誤っている」のでもありません。
どちらの動き方も、その状況に合わせて、「自分が何をしているか」を感じながら、立ち上がるならば、問題ありません。途中でつらいと感じたら、戻ればよいのです。
人の動きに「正しい動き方」というものはありません。「何をしているのか感じないで動いている」ことが危険なのです。
わたしが普段立ち上がるときには、ここにあげた動き方はしません。別の動き方のほうがわたしにはとても楽なのです。
