実はラバン自身もこの辺の表記については流動的でした。
同じことについて表記が変わっています。
たとえば、"The Mastery of Movement"という本で Flow, free, sudden, gentle, firmと表記されているものが、"Effort"という本では Control, fluent, quick, light, strongとかかれています。
「言葉」に意味はないのです。
実際の動きを感じて、言葉の意味を理解しなければなりません。
ラバンは動きを図で示すことを考えました。
「空間、時間、重さ、なめらかさ」を軸として使うと、動きを図で表すことができると考えました。
その図に Effortgraph と名付けました。
Effortgrapf 自体は、このサイトでは重要ではありませんが、教養として簡単に解説します。
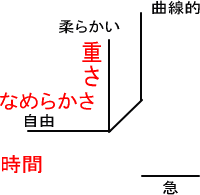 釣り竿を振るつもりになってください。
釣り竿を振るつもりになってください。どんな動きをするでしょう?
わたしなら、釣り竿を持った手首を緩くして、ピュッと振ります。
このときの動きは、「手首を自由にして、円弧を描くように柔らかく素早く振る」と表現できます。
この動きを表現したEffort graphが左の図です。
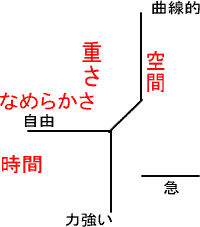
次に相撲の動きを考えてみます。
相撲では、「力強いけれども、かちかちにならず、相手の動きを見て柔軟に素早く動く」ことが良いことでしょう。
この動きをEffort graphで表現すると、左のようになります。
上の図から文字を抜くとこのようになります。

このような図を描いて、ある人の作業を表現してみます。
すると、下に棒が描かれる仕事は、肉体的な力を必要とすることがわかります。
力強い男性が適しているかもしれません。
逆に上の左の方に棒が描かれる仕事は、女性に向いているのかもしれません。
ただし、最近は女性でもアスレチッククラブに通い筋肉を鍛えている人もいますから、一概には言えません。
他の使い方もできます。
仕事に必要な動きの流れをEffort graphを使い、記録していきます。
もし、図が少しづつ変化するなら、その動きの連続はそんなに難しくはないでしょう。
働く人も楽にできるでしょう。
反対にEffort graphが激しく変化し、それが継続するようなら、その仕事をするには困難が伴うでしょう。
このように、動きを記載することで、問題点を見つけやすくなり、改善しやすくなります。
こうして、働く人が楽になり、仕事の効率が上がるだろうとラバンは考えたのです。
しかし、Effort graph 自体は、介助には大切でありません。
大切なのは、「動き」を「時間、空間、重さ、なめらかさ」という要素に分解して考えることができるという発見にあります。