

ブレークダンスから派生したものに、ロボットダンスがあります。
ある日、ネットサーフィンをしていると、おもしろい映像を見つけました。
それはロボットダンスでした。ブレークダンスのように激しい動きはしませんが、とても自由に動きます。
わたしの見たのは、David Elsewhereのビデオでした。これはすごいです。ぜひ、見てください。
初めて見たときには、「この人には関節がないのか」と思いました。
でも、じっと見ていると、わかってきたのです。
Davidは自分の体の各部分の動きの範囲を知っています。そして、それぞれの部分が全体としてどのように動くかを熟知しています。
さらに地球の引力と仲良く、インタラクションしているのです。
ですから、見ていて無理がないのです。力任せに動いたりしません。だから、くにゃくにゃと見えますが、じつはちゃんと関節で動いています。
いや、ちゃんと関節で動いているから、くにゃくにゃに見えるのです。
普通の人は関節で動かずに、違うところで動こうとして、力が入ります。
それを「普通だ」と思ってみている私たちの目がおかしいのでした。
David Elsewhereは、どこでもない地球の大地の上にしっかり立って、自由に動いています。
Davidのダンスのムービーを ユーチューブで見ることができます。
"David Elsewhere"で検索してください。
すごい!
コンテスト(?)の模様も見ることができます。
Detourの今は、なくなってしまったページには、Elsewhereの紹介がありました。
なぜ、Elsewhereなのか?
1)踊っているときは、自分の状態を忘れて、どこか別のところ"Elsewhere"にいるから。
2)自分のスタイルを他の人が目指したことのない境地、行ったことのない境地に持っていきたいから。
ひぇー、すごい。
これは、「秘密の小窓」で紹介している、サイバネティクス、全体論、内言論、学習理論、心理療法と同じことが端的に語られています。
以下にわたしが勝手に読み取ったことを書いてみます。
(これはわたしが「こう読んだ」というものです。翻訳ではありません。
2011年現在、ここに紹介している文を書いたページは削除されています。
ですから、参考にするか、管理人の妄想としてお読みください。)
練習と考え方
数年に渡り、わたしは自分がより良いダンサー、独創的なダンサーになるために重要と思う考え方に練習を合わせるようにしてきました。
ここに掲げたことがすべての人に適用できるとは思っていません。
ただ、自分が良かったと思うものを知ってもらいたいだけです。
これを読んだ人が、「なるほど!」と思おうと、「違う!」と思おうと、それは自由です。
「自分であること」
古くさく聞こえるでしょうが、わたしが考え方の中でもっとも大切なものの一つが「自分であること」です。
「自分であること」で、他の人が期待することや流行に惑わされずに、自分が本当にやりたいダンスを踊ることができます。
「自分であること」で、自分が心から望むことをでき、いつでもやる気満々でいられます。
マズローの言う「自己実現」というところでしょう。
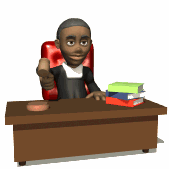 「自分の判断を信じること」
「自分の判断を信じること」
これは「自分であること」と深くかかわっています。
本当にあなた自身であるためには、ある程度自分の判断を信頼しなければならないからです。
「自分の判断を信じる」は、ダンスに対する自分の好みや創造性に自信を持つことです。
観衆からの反響を聞くことはたしかに役立ちますが、それでも、わたしは自分自身の判断を信じるのです。
エリスの論理情動行動療法に近いです。
 「いつもダンスする」
「いつもダンスする」
心と体が自由なときは、いつでもダンスするようにしています。
電子レンジでランチを温めて、を待っている間や、スーパーマーケットで、商品を見ながら歩いているとき、いつでもなにかしらダンスの練習にしています。
いつでも、どこでもダンスをするという習慣をつけると、一日中がダンスのセッションになります。
「試行錯誤」
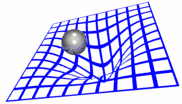
ダンスはたしかにアートの一種ですが、それでも自分自身の動きやスタイルを作り出すために、多くの試行錯誤をくり返すことで、ダンスをもっと科学的にできます。
わたしのレパートリーの中のかっこよい動きは、どれも、実際に使うには不自由な動きを含んでいます。
自分の経験からいえることは、いろいろな動きを作ろうと試せば試すほど、かっこよい動きを作る能力が増すということです。
これはサイバネティクスと構成主義教育理論そのもの。
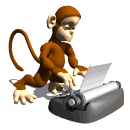
「動きを書くこと」
思いついた動き、セット、ルーチン、スタイルは、単なるアイデアに過ぎないものまで、すべてを列記して、覚えておきます。
そのリストをいつも持って、練習の時に参考にしています。
これは内言論です。自分の動きを、まず内言にして、それを自分にだけ分かる外言として記録します。

「反復練習」
新しい動き、セット、ルーチン、スタイルを作り上げて、残しておきたいたときは、意識しないでもできるようになるまで、つまりそらでできるようになるまで、演じることはしません。
その動きをくり返し<覚え込みます。とにかく、くり返します。何度も何度も何度も・・・。
これは「一般意味論」でも、「内言論」でも解説可能です。非言語的な記憶、非言語的な表現について語っているからです。

「誰もやっていないことを探す」
ダンスの中には独創的なものにしやすい分野があります。まったく新しいものがたくさん残されていて、たいして探索されていない分野があります。
アートという視点から見れば、人の通らない小道ほど、役立つものが残されています。
わたしはそういう道を歩いてきました。
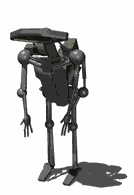
「ダンスを越えたものを求める」
ダンスは動きを基礎にするアートです。
そして、ダンスという視点を超越してみると、息をのむような動きの世界があります。
マシン、自然、カンガルーなどです。
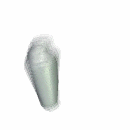 「スタイルを混ぜる」
「スタイルを混ぜる」
オリジナルに見えるものはすべて、既存のものをオリジナルなやり方で混ぜたものに過ぎません。
ブレークダンスはその典型的な例ですし、Detours Parallelでもおなじことを見られます。
この前提に立てば、自分自身のものだと言えるものを作り出すまでは、動き、スタイル、他の分野から参考にしたものを混ぜ合わせることが、独創性に到達するのに役立つ方法でしょう。
 「ラベルを無視する」
「ラベルを無視する」
ラベルは暗黙の境界を作ってしまうので、独創的であろうという志を邪魔します。
たとえば、「Bboy(訳注 ブレークダンスのダンサー)になろうと思うなら、こうしなければならない」と言ったとします。
しかし、そんなことはできないのです。
なぜならば、なにかを「しなければならないと考えること」自体が、Bboyであるための独創性をなくすことだからです。
もちろん、わたしのやりたいことは、従来からある何らかの分野に納まるものではありません。
それでも、独創的な「混ぜ合わせ」なのです。
「新しいものが見つかったら、それには名前なんか無いのさ。新しいものは言葉では表現できないのさ」とベニー・ゴルソンは言いました。そのとおりなのです。
これは一般意味論そのもの。
(注 Bboyとこの後出てくるMr.Animationについては、ユーチューブで検索してご覧ください。ビデオは必見です。
また、ベニー・ゴルソンはテナー・サックスのジャズ・ミュージシャン。スウィング・ジャズにハード・パップを融合させていったと言われる。ジャズの名曲、「アイ・リメンバー・クリフォード」の作者。)
「潜在能力を引き出すためには、自分自身の影響を利用すること」
人間には、自分に影響を与えるものを、まねしようという性質があります。
人がなにかを習おうとするときには、特に初心者では、ある程度まねをするということがあるでしょうし、必要だと思います。
経験から言えば、潜在能力を引き出すために、自分自身の影響を理解して使い始めたときに、より独創的になれました。
それまでの自分自身を作るのに影響を与えた動きやスタイルも変えることができるし、改善することさえもできると知りました。
このために役立ったことの一つは・・・
これはサイバネティクス。フィードバック理論そのものです。
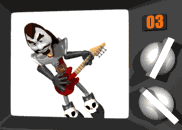 「参考としてビデオではなく、記憶を信頼すること」
「参考としてビデオではなく、記憶を信頼すること」
自分が普段見る動きを意識しないうちにまねする性質を、多くの人が持っています。
わたしも同じ性質を持っています。
ビデオはくり返してみることでどうしても物まねになってしまうという危険が高いので、どちらかというと良くないものです。
わたしが頼りにしなければならないものは自分の頭の中の記憶です。
ですから、まねに陥ることのないように、Skywalker や Animationのビデオもたまにしか見ないようにしています。
記憶だけをダンスの指標とすることで、創造性を高めることができます。
そうして、外部からの影響を自分の中の改革に向けることができます。
これもサイバネティクス。特に行動サイバネティクスと言われる分野の考え方です。
 「一人で練習すること」
「一人で練習すること」
誰かと一緒に練習するよりも、一人で練習する方がうまくいくと思います。
他人の目があるときには、練習ではなくダンスで演じたくなるからかもしれません。
他人と一緒に練習しているときは、どうしても自意識過剰になるので、うまく実験できません。
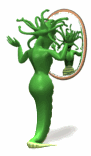 「鏡を使う」
「鏡を使う」
鏡を使うことはとても役立ちます。
すぐにフィードバックがかかるからです。
鏡を使うと、自分の動きを瞬時にチェックできて、自分で批評できます。
鏡を使うことについての悪い点は、ただひとつ、鏡を使うことに頼りすぎると、鏡がないとうまく演じられなくなることです。
そうならないために、わたしは鏡の前で練習するのと同じくらい、鏡なしで練習します。
これは行動サイバネティクス。最近では認知科学と言われる分野です。
 「自分の動きをビデオ撮影する」
「自分の動きをビデオ撮影する」
自分をビデオで時々撮影します。
鏡を使うと同じように役立ちます。
唯一の欠点はフィードバックが瞬時ではないことです。
つまり、そのときやっていることを、そのときすぐには見られません。
それでも、ビデオは鏡にない利点があります。
ビデオを使えば、鏡に映る姿に注意せずに、ダンスに集中できます。
ビデオ撮影しておけば、鏡では見づらいスピンやグラウンドの時にも、何をしているかを観察できます。
いろいろな角度から自分のやっていることを観察できるのです。
これも行動サイバネティクス。遅延型の視覚によるフィードバックです。
ねっ、すごいでしょ!
この人は、人間というものをよく知っているのです。