
ここに書いてあることは、「理論」です。
「理論」は実践をきっかけとして、アイデアを得て実践の一部を切り出したものです。
ここに書いた「理論」は正しさを主張しません。
読んだ人が実践の中で、その妥当性を確認してください。
多くの人がかつて考えていました。
圧力により、組織の血流が悪くなり、虚血で組織が壊死になることで褥瘡ができる |
本当なのでしょうか?
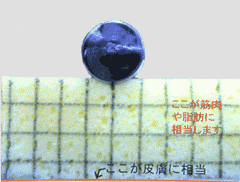 左のアニメは、筋肉を骨が押すモデルです。
左のアニメは、筋肉を骨が押すモデルです。一番強く押しつぶされるのは、骨に近くてやわらかい組織であることがわかります。
このとき、軟部組織の外側から骨が押している力を「外力」といいます。
この「外力」によってスポンジの内部に変形が生じます。
Aの点にかかる「力」を見てみましょう。
押し付ける力を「圧力」と呼びます。
骨が下に押し付けると、支持面はそれを支えますから、Aの点には上と下から圧力がかかります。
Aの点には左右に引っ張る力も働いています。
これを「張力」と呼びます。
押し付けることで、組織を引き裂く力が働きます。
Aの点より内側は押しつぶされていますが、その外側は比較的つぶされていません。
組織自体の弾性により広がろうとします。
この2つの「力」は反対に向いています。境界にあるAの点ではずれる「力」が働きます。
これを剪断力と呼びます。
「断ち剪る(たちきる)力」です。
剪断力は上下方向だけでなく、左右前後にもかかります。
骨が組織を押すだけで、圧以外の力がかかります。
このように、内部に変形を作る力、圧力、張力、剪断力をまとめた「力」を「応力」と呼びます。
一般には「内部の歪(ひず)み」と呼ばれるものです。
従来、「圧力がかかるから褥瘡ができる」と言われましたが、正確には応力がかかるからだと言われます。
ただし、「応力」は測定できません。測定しようとしてセンサーを内部に入れたとたんに条件が変わってしまいます。
ですから、工学部では、コンピュータのシミュレーションで研究します。
そこが応力理論の限界です。
最近は圧力ではなく、「ずれ力」という言葉がはやってきています。
「ずれ力」は皮膚の表面に歪みセンサーを貼り付けて、皮膚表面とセンサーの間の歪みを測定し「外部の歪みの測定値」です。
内部の「応力」ではありません。
組織内部の横方向の剪断力を「推定」していますが、上で述べたように応力は直接測定できませんから、信頼性はありません。
「ずれ力」は横方向の剪断力を体の外側にかかる力から推測しているだけです。
「ずれ力が低下したから、改善した」とか、「ずれ力が高いから褥瘡になりやすい」と言うのは、「貧乏だから心が貧しい」とか、「女だから優しくしなさい」というのと同じです。
保証がありません。
参考にしかできません。
大切なのは自分の体で確かめることです。
自分の体には、「感覚」というシステム内部の歪みセンサーがついています。
自分の体の内部のセンサーの大切さについは、キネステティクス的褥瘡ケアの解説を読んでください。
では、このモデルの「応力」が本当に臨床を説明できるのかを見てみましょう。
科学とは、実践で気づき、抽象化し、実践で確認することですからね。
この最新のモデルの歪みを見ていると、骨が軟部組織を押しつぶしたときに生じた応力は骨の近くでもっとも大きくなります。
この「歪み=応力」が骨の近くの組織の血管を押しつぶして、血流を悪くして、組織が酸素不足で死んでいくと言われます。
だから、皮膚表面がなんともないのに、皮膚の下で壊死が進んでしまうⅢ度やⅣ度の褥瘡ができるのだろうと、多くの人が今考えています。
「応力」により、組織の血流が悪くなり、虚血で組織が壊死になることで褥瘡ができる |
しかし、これも本当なのでしょうか?
まずは、症例からみてみましょう。