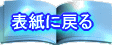
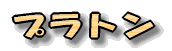
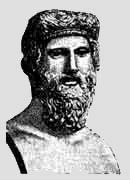 ソクラテスの死後、12年たってプラトンは自分の学園アカデ イアを作りました。
ソクラテスの死後、12年たってプラトンは自分の学園アカデ イアを作りました。
ここで弟子たちに講義をし、自らの思索を深めました。
アカデイアはギリシア哲学の新しい殿堂となり、有名になります。
弟子たちが集まりました。
その中の一人が、アリストテレスであり、現代にまで影響を与えています。
プラトンはソクラテスとの対話を通し考えたことをまとめていきます。
ソクラテスは「善とは何か?」と問いました。
プラトンはその答えとして、
「『善である』 と認められるものには、具体的なものとは関係なく、純粋に思考によってのみとらえられる本質がある。
そのものの本質が『善』であるから、そのものが『善である』とわかるのだ。
そのものがなくなろうと『善』という本質はなくならない」
と考えました。
この本質を「見る」ideinというギリシア語から 作ったイデアという言葉で示しました。
これを「イデア論」と言います。
「善」、「美」、「勇気」、「節制」というイデアが存在するけれど、イデア自体は見たりさわったりできない。
ただ、思考によってだけとらえられる。
そのイデアを持つものが「善い人」「美しいもの」「勇気ある人」「節制ある行い」として目に見える体験できる存在になっているというのです。
たとえば、「美しいもの」には、「美のイデア」が存在するから、それを見た人は「それは美しい」と感じるというのです。
つまり、「美しさ」は対象の中に あり、その「美のイデア」が、見ている人に伝わるということです。
これは、実は誤解です。
ベイトソンの認識論で書き
ます。
プラトンによれば、
「イ
デアがあることだけは考えるとわかるが、イデアの全貌を把握したり理解したりすることは人間にはできない」
ということになります。
人間が考えてわかるところはイデアの一部です。
そのイデアの一部について知ったことをepisteme(エピステーメー)と呼びました。
この項の最初で哲学が存在論と認識論 (epistemology)の2つからなると書きました。
Epistemologyはepistemeとlogos(理論)からできた言葉です。
人間 が考えないでもわかることは、ドクサ(doxa)と呼ばれました。
プラトンの考えを要約すると、普段何も考えないときには、ドクサを見ていて、考えるとイデアに近づいていって、エピステーメーが得られるけれど、イデア
そのものは手に入らないのです。
ただし、プラトン自身はイデアについて厳密な定義はしていません。
神の領域です。わからないのです。
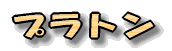
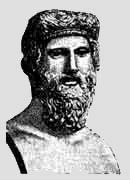 ソクラテスの死後、12年たってプラトンは自分の学園アカデ イアを作りました。
ソクラテスの死後、12年たってプラトンは自分の学園アカデ イアを作りました。