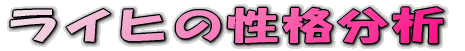
1936年には、ライヒは、筋肉の緊張、収縮に興味を持ち、精神分析から離れていきました。
筋肉の収縮をはじめ、体内の電気的事象や顕微鏡的事象を調べました。
ライヒは、リビドーは実在のエネルギーであると考えました。
そのエネルギーが性的満足感=オーガズムを作る元であると考えました。
そして、そのエネルギーにオルゴンという名前を付けました。
実際にオルゴンを内蔵する粒子が生物に存在するのを顕微鏡で発見したと思い、ビオンという名前を付けました。
この後、ライヒは「オルゴンを集めて神経症の治療ができる」と主張しはじめました。
これには、オスロ大学のほかの精神分析医が反発し、新聞紙上でキャンペーンを張りました。
1939年、ライヒはオスロを去り、アメリカのニューヨーク州社会学ニュースクールにで心理学を教えることとなりました。
ここで、ライヒは2度目の結婚をします。
ライヒは、「筋肉の鎧」を解いて、体のエネルギー、つまりオルゴンの流れを良くすることが、神経症の治療になると信じました。
クライエントには性格分析や、言葉のコミュニケーション、指導、目標の設定、問題と抵抗についての話すことで治療しました。
1940 年には、大気中にオルゴンを発見したと思いました。
この「オルゴン」については、現代の科学は否定的です。
日本で発行されている「性格分析」の翻訳本には、国際精神分析学会の分析医のコメントが載っています。
「ライヒは、『性格分析』を書いたときまで、正常だったが、その後は精神を患っていた」
うーん、確かにオルゴンやビオンは、現在の科学でも証明されていないですから、・・・・
インターネットで「オルゴン集積器」が売られていたりします。
わたしはおすすめしません。
しかし、「体」が「心」を支配しているかもしれないことに気づいたという点では、ライヒの業績はすばらしいと思います。
というわけで、オルゴンの真偽は問わずに、今しばらく、ライヒの生涯を追ってみましょう。