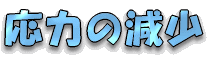
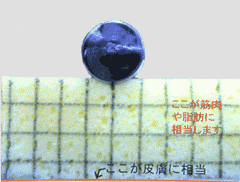 左のアニメーションは、スポンジをダンベルで押したものです。
左のアニメーションは、スポンジをダンベルで押したものです。これが体の中の「力」のかかり具合のモデルです。
ダンベルは骨、スポンジが筋肉です。
よく見てみると、ダンベルつまり「骨」に重さがかかって、スポンジつまり「筋肉」を押すと、一番下になっている皮膚に近いところではなく、骨に近いところのスポンジが一番強く押しつぶされていることがわかります。
これは第1回日本褥瘡学会で北海道大学工学部の高橋助教授が発表しました。
骨(ダンベル)や支持面は筋肉(スポンジ)の外側から押します。
このような力を外力と呼びます。
筋肉の中に生じる力は内部の力=内力と呼びます。
骨が筋肉を押すと、内力が生じます。
このように「外力に呼応して生じた内力」を応力と呼びます。
つまり、体の重さがかかると、「骨に近いところの組織にかかる応力が最も大きい」のです。
| ストレスについて |
応力は英語で stress ストレスです。もともと、上で述べたように、力学の用語でした。 ハンス・セリエは医学生の時に、ある種の患者は、違う原因をもとにして、同じ反応をしていることに気がつきました。 力学で応力の発生とよばれるものと同じことが、人間の体でも起こっているのではないかと感じました。 卒業し生理学者となり、実験をして「ストレス理論」を発表しました。 人間は寒冷、高熱、外傷、振動などの物理化学的刺激に対しても、人間関係、不安、悲哀、喜びなどの精神的刺激に対しても、同じ反応を起こします。 それが体に変化を生じさせます。 このときの刺激をストレッサー、それに対して起こる反応をストレスと呼びます。 このストレスが、潰瘍や鬱の元となるというのです。 ストレスによる疾患の代表は、消化性潰瘍です。 ストレス潰瘍 stress ulcer と名前が付けられました。 褥瘡の英語はpressure ulcerです。「圧力」でないことを表そうと、stressという単語を入れると、stress ulcerになります。 これは精神身体医学で使われるストレス潰瘍とまったく同じになります。 もともと力学で使われていたストレスという言葉を、精神身体医学で使われたために、今、褥瘡に応力が関係していることがわかっても、命名に使えないという不思議なことが起こっています。 |