「学習」は、どのようにして行われるのでしょう?
「教育」とはどのようにして生じるのでしょう?
わたしは知らなかったのです。
でも、ヴィゴツキーの社会教育論と「内言論」、ベイトソンの認識論、サイバネティクス・システム理論、そして行動主義理論、構成主義理論を知ったときに、自分がどのようにして学習していたのかを知りました。
とんでもない話です。
自分が「学習」してきたのに、何が起こっていたのかを知らなかったのですから。
内言論で、「内部言語=内言」について説明しました。
「外側の世界」の体験から外言の意味を知り、内言が作られます。
バラの花を見ることで、「薔薇」という「言葉」の示すものを知り、「薔薇」という言葉を頭の中で思い浮かべることで、バラのイメージが「内側の世界」に作られます。
そうして、初めて「バラ」を考えることができます。
| コラム |
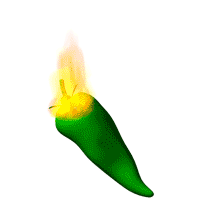 よく考えると、当たり前の話です。 唐辛子を食べたことのない子供に「とんでもなく辛いよ」と言ってもわかりません。 ほんのちょっと食べてみれば、「とんでもなく辛い」と言った人の「思っていたこと=情報」はわかります。 でも、それは「体験」の後です。「言葉」で理解したのではありません。 「言葉」の意味を体験で理解したのです。 |
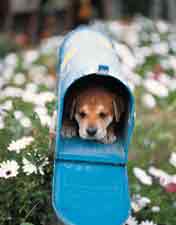 この犬は 「切手を貼っていないものは、 郵送されないこと」 を学習するでしょう。 |
「一般意味論」のページでは、ウィトゲンシュタインが「哲学探究」の中で、言葉の定義には言葉が示すものを直接見せて「言葉」を教える「直示」と、言葉で言葉を示す方法の2つがあるとしたことを書きました。
フェルデンクライスは、「人は体験から学ぶ」と言いました。
サイバネティクスでは、「生きているシステム」には外部から情報は伝わりません。
外部から来たエネルギーが内部の変化を作り、その「変化」という「違い」が情報として受け入れられます。
「生きているシステム」は、そのシステムが体験したことしか学習できません。
どの理論も同じ結論にたどりつきます。
人間を含む「生きているシステム」は、体験から学習します。