
ここで、老人の立ち方と若い人の立ち方を比べてみましょう。
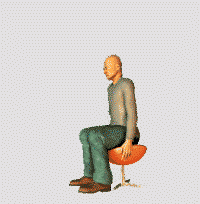 老人に多いパターンを左にアニメーションにして示しました。
老人に多いパターンを左にアニメーションにして示しました。頭をうなづくように前に倒します。
胸郭を前に倒します。
頭と胸郭が前に傾き、腰椎を引き骨盤を引っ張ります。
骨盤が前に傾き、股関節が前に行き、大腿骨を前に押します。
膝関節、足関節が屈曲すると、足に重さがかかったと「感じます」。
足に重さがかかったところで、骨盤を持ち上げて、その後から胸郭と頭を骨盤の上に積み上げます。
このようにすると、腰椎が前に傾き、その後で骨盤が傾きます。
大腰筋が、頭と胸郭の協力を得て、腰椎を引いて前に傾け、その後で大腰筋と腸骨筋が協力して骨盤を前に傾けています。
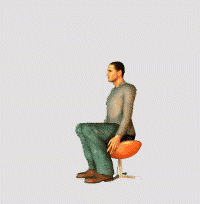 脊柱を曲げずに、立ち上がることもできます。
脊柱を曲げずに、立ち上がることもできます。頭が天井に引っ張られているように、脊柱をのばしたまま、上体を前に傾けます。
このとき、前のページで説明したように、大腰筋と腸骨筋が協力して、腰椎から上を骨盤の上に直立させています。
大腰筋と腸骨筋が腰椎を骨盤の上に立たせているので、上体をそのまま前に傾けると骨盤が傾きます。
骨盤が前に傾くと、股関節が前に出ます。
すると、骨盤が大腿骨を押します。
そして、大腿骨が大腿の中で前に進みます。
両足に重さがかかったら、そのまま両足の上で下肢をのばせば、楽に立ち上がります。
このようにして立ち上がるときには、脊柱の前後の筋肉の緊張は最小限になります。
このようにすると、はじめから腸骨筋と大腰筋が協力して収縮しています。
上の2つの立ち上がり方では、立ち上がる資源としての大腰筋の使い方が違います!
若いときは、筋肉がついています。
頭、胸郭、上肢という上体を、大腰筋の力で骨盤の上にのせておくことができます。
ですから、骨盤をちょっと前に傾けるだけで立つことができます。
脊柱の周囲の筋肉を収縮させて脊柱を縮めなくてもできます。
背中は楽になります。
しかし、老人になると、たいていは大腰筋が弱くなります。
座っているのがつらいという人は、たぶん大腰筋も弱っています。
上体を大腰筋の力で骨盤の上にのせておくことができません。
しかし、そのようなときには頭と脊柱を使って、骨盤を前に傾けることができます。
2005年現在、転倒予防のために、老人に運動をさせて大腰筋を鍛えることが推奨されます。
しかし、上に書いたことを理解すれば、筋力アップをしなくとも、同じ効果を得られるかもしれません。
ひとつのことをいろいろな方法で実行できることは能力の高さです。
もちろん、立ち上がった後には、脊柱の周りの筋肉をゆるめることが必要です。