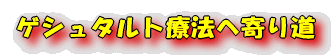コミュニケーションにはいろいろな定義があります。
どれかが正しいというものではありません。
コミュニケーションという「関係」が先にあったのです。
それに名前を付けました。その名前を付けた後に、いろいろなことが分かってきて、くっつけられました。
ですから、コミュニケーションは、コミュニケーションを論ずる人の数だけ定義があっても不思議でありません。
| コミュニケーションのいろいろな定義 | |
| インタラクション・プロセス説 | インタラクションとしてのコミュニケーションが社会の基本的単位である |
| 刺激−反応説 | コミュニケーションは刺激,反応,学習の連続によって習得されるもので 社会調節,管理の手段となる |
| 意味付与説 | 意味を相手に伝えるプロセスがコミュニケーションである |
| レトリック(修辞)説 | 古代レトリックの観点からコミュニケーションを捉えようとする(いろいろな言い方で何とか、考えていることを伝えようとする) |
このサイトで、採用しているのはインタラクション・プロセス説と刺激反応説に近いかもしれません(すべてを学習していないのでわかりません)。