
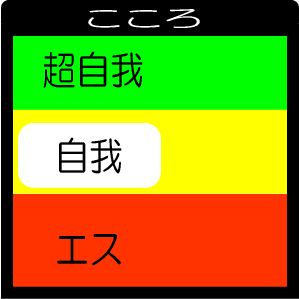 自分の中にエスと超自我しかなければ、自分の中でいつも葛藤が生じます。
自分の中にエスと超自我しかなければ、自分の中でいつも葛藤が生じます。これでは生きていけません。
そこで、の折り合いをつける仲立ちをするものがあります。
フロイトはこれをドイツ語で Das Ich(ダス イッヒ と読みます)と呼びました。
ich は日本語では「わたし」、英語では I です。
あなたが日常的に自分を人間として自覚している「わたし」のことです。
「わたし」についてはよく知っているでしょう?
あなたが意識している自分は、たいてい「わたし」です。
Das Ich は ich という代名詞を名詞化したものです。
ところが、英語に翻訳されたときに、これにラテン語で"ego"をあてました。
ここで混乱が生じます。
ラテン語は人称、時制、仮定か現実か(文法では「法」と呼ばれます)によって動詞が厳格に多様に変化します。
ですから、主語はいりません。
たとえば、"cogito ergo sum"(コギト エルゴ スム)という言葉があります。
cogitoは「思う」の一人称単数現在形です。
cogitoだけで「わたしは思う」になります。
あなたでも彼でもなく、わたしが思うのです。
ergoは「だから」という意味です。
sumは「存在する」の一人称単数現在形です。
「わたしは存在する」です。
"cogito ergo sum"という文には主語はありません。
しかし、動詞の変化の中に「わたしが」という意味が含まれています。
ですから、これだけで「我思う故に我あり」という意味になります。
"ego cogito ergo ego sum"と書いても、間違いではありません。
しかし、必要のない主語を入れると、意味を強調してしまいます。
ラテン語のegoはドイツ語のichより強烈な印象を与えます。
英語に翻訳されるときには、一般の人になじみ深い I ではなく、"ego"が使われました。
アメリカではラテン語の "ego" で広まりました。
ego は英語では特殊な言葉です。
日本でも「わたし」ではなく、「自我」と翻訳されました。
自我も日本語では特殊な言葉です。
本来、もっとも身近に「感じられる」はずの「わたし」が、"ego"やら「自我」という聞き慣れない「名前」で呼ばれるようになりました。
「自我」というとても強い感じを受ける言葉ですが、意味するものは、あなたが慣れ親しんだ「わたし」そのものです。
自分の生活を思い出してみましょう。
何を基準にして行動していますか?
快楽原則でしょうか?
道徳原則でしょうか?
たぶん、そのときどきで変わるでしょう。
快楽だけを追いかけては社会からはじかれます。
道徳ばかりを追いかけると苦しくなります。
道徳は外部の規則を「丸飲み」しているからです。
「わたし」は快楽原則にも従わず、道徳原則にも従わず活動します。
「わたし」は大岡裁きのような現実的な解決を求めます。
このような現実的な解決を図るやり方を現実原則 Realitaetsprinzipsと呼びます。
自我は現実原則 Realitaetsprinzip に従います。
この「わたし」がしっかりしていると、エスや超自我を上手にコントロールして生きていけます。
社会と折り合いもつけ、「生の欲求」に従い、健全な「性」を体験してリビドーを生きるための原動力にできます。
また、リビドーを「性」に向けず、他のことに向けること(昇華)で、より能力の高い人間として生きることができます。
逆に自我が弱いと、エス、自我、超自我のバランスが崩れて、上手に生きられません。
人間としての能力が損なわれてしまいます。
この状態をフロイトは「神経症 Neurose ノイローゼ」と呼びました。