
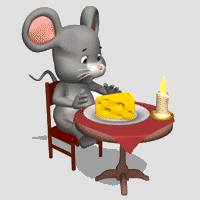
この「パブロフの犬」の後に、スキナーが「オペラント学習(オペラント条件付け)」というのを発表しました。
箱の中にネズミをいれて、ネズミがレバーを押すと餌が出るようにしました。
ネズミは餌という「ご褒美」がほしくて、レバーを押すことを学習するというのです。
オペラント学習付けとは、「行動の動機を学習させること」です。
スキナー箱と呼ばれます。
「条件付けられた反射」と「オペラント学習」が、学習のモデルになりました。
「学習は行動の変容で測定できる」と考えられました。
このようにして、アメリカで流行したのが、刺激-反応理論です。
刺激Stimulation と、反応 Response の頭文字をとって、SR主義とも言われます。
「刺激を与えると反応することで、行動が変わる。学習は行動の変容である」というのです。
行動主義と言われます。
「わかっているなら、やりなさい」とか、「うまくできないっていうことは、わかっていないからだ」と言うのを聞いたことがあるでしょう。
これが行動主義理論の教育です。





行動主義では、教育の成果は行動の変化を計量することで判定します。
刺激から反応までの間に、学習者の中で何が起こったかは問題にしません。
SR主義では心の存在は問いません。
行動主義に基づけば、結果を出しやすいくなります。