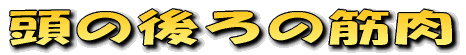
 ここまで見てきたように、頭は首の上でいろいろな動きをします。
ここまで見てきたように、頭は首の上でいろいろな動きをします。この動きは首の骨から頭につながっている筋肉の働きによります。
左に示した絵は、1742年のフランス人、Gautier d'Agotyの描いた解剖図です。カナダのDalhousie大学の資料館のページからいただきました。
後頭部から首にかけて、たくさんの筋肉があることがわかります。
ひとつひとつの筋肉の名前と働きを覚えるのは無駄です。
これらの筋肉はそれぞれが協力して働き、いろいろな動きを作り出します。
「正しい動き」はありません。
ですから、「ここの筋肉を使いなさい」という指導は無駄です。また、そんなことをしたら、自然な動きはできません。
できることは、これらの筋肉を無駄に緊張させないことです。
使いもしないときに、これらの筋肉を緊張させると、首の骨の動きを邪魔します。背骨を使えません。
首の前側の筋肉が収縮するときに、後ろ側の筋肉も収縮させれば、文字通り、首を縮めてしまいます。
そんなことをしたら、やりたいことはできません。
「頭と首とは多くの筋肉でつながれている」と理解したら、それらをゆるめること、最小限度の緊張だけにすることです。
そうすると、首は自由に動けます。首が痛くなったり、肩がこったりすることもなくなるでしょう。
 では、首の骨、つまり「頸椎全体の動き」はどうなっているのでしょうか?
では、首の骨、つまり「頸椎全体の動き」はどうなっているのでしょうか?